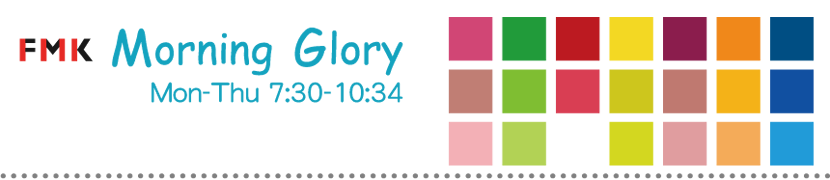熊大ラジオ公開授業「知的冒険の旅」 徳野貞雄先生
あらゆるジャンルの注目の人にインタビューする
「ヒューマン・ラボ」。
11月から3ヶ月間にわたって
スペシャル企画でお届けしています。
題して「FMK Morning Glory ヒューマン・ラボ
熊大ラジオ公開授業・知的冒険の旅」。
毎回、熊本大学の先生を講師に迎えて、
さまざまジャンルの研究テーマについて
お話をうかがいます。
第9回の講師は徳野貞雄先生です。

Q① お名前と職業・所属を教えて下さい。
名前:徳野貞雄(とくのさだお)
所属:熊本大学文学部総合人間学科地域社会学
プロフィール:
1949年大阪府貝塚市生まれ。
1987年九州大学大学院文学研究科博士課程修了
1987年山口大学人文学部助手
1989年広島県立大学経営学部助教授
1997年熊本大学文学部地域科学科社会学助教授
その間にシェフィールド大学(イギリス)客員研究員。
1999年現職
食と農の専門家として日本全国の農村に出かけ、
フィールドワークをこなす活動派。
全国合鴨水稲会世話人。
『道の駅』命名者。
上記肩書き以外の主な役職:
九州農業・農村デザイン塾々長
九州番頭さんの会主催者
全国合鴨水稲会世話人
国土交通省地域振興アドバイザー
Q② 徳野先生の専門である
「農村社会学、農業社会学、地域振興論」とは、
どんな研究ですか、わかりやすく教えてください。
農村を軸に地域社会の構造変動や
住民の生活構造についての研究
(過疎地域論や混住化社会論などを含む)。
担い手問題や農業後継者問題および
有機農業運動など農業問題における
人間の社会的領域に関する研究。
関連して現代社会における消費者(国民)
の食生活構造など。
現代の高度産業社会化の
日本における『食と農』に関する研究を
農業社会学として提唱している。
「マチおこし」「村おこし」のシステム開発や
地域活性化集団の運営および農山村型
第三セクターに関する研究。
・社会学の他の領域にもつよい関心がある。
Q③ 徳野先生がこの研究に取り組むことになった
「きっかけ」のようなものがあれば教えてください。
山口大学で過ごした学生時代に、
研究テーマを女工の実態として社会を探ろうと
試みた。社会に対する関心が強く、その後、
農村社会学が研究の主軸となった。
社会学というのは、人間の共同性の研究。
共同性とは、具体的現実における生活構造に
他ならない。つまり、現実の中に加わらないと
社会は見えてこない。現実に加わる術が実践であり、
実践によってしか見えてこない社会の問題がある。
机の上だけでやる研究は社会学学にすぎない。
真の社会学とはよべない。
「自分が生きて行く」こと、
「生き続けて行くこと」を探求し続ける。
Q④ 徳野先生の研究テーマについて。
Q④ 徳野先生の研究テーマについて。
家族は何人ですか?と尋ねると、その時一緒に
暮らしている人数を答える人がほとんどです。
暮らしている人数を答える人がほとんどです。
これは、「家族」と「世帯」を混同しているからです。
世帯は、同居している人数、家族はたとえ離れて
暮らしていても、空間を超えて機能するものなのです。
それは、近所に住んでいようが、
海外と離れていても、「家族」です。
また、世帯をみると日本は戦後経済発展とともに
単独世代、夫婦二人世帯が増えた。
世帯数が増えれば、家電製品や車、
住宅建築が増える。
そうして、経済を発展させてきました。
しかし、現代は本当に必要なものはすぐに手に入る、
モノがあふれていると言ってもいい。
モノがあふれていると言ってもいい。
そんななか、これからの「幸福」は、モノをどれだけ
持っているかではなく、身近な人とどれだけ
つき合えるかで決まってきます。
身近にいる子どもや孫、隣人でも友人でもいい、
日常的に交流ができることが充実した生活を
送ることができるでしょう。
持っているかではなく、身近な人とどれだけ
つき合えるかで決まってきます。
身近にいる子どもや孫、隣人でも友人でもいい、
日常的に交流ができることが充実した生活を
送ることができるでしょう。
Q⑤ これまでの活動を通じて、
最も印象深いエピソードをお願いします。
現代は家族が崩壊したというが、
家族が無くなったわけではく、
社会構造が変化しただけ。
それを考慮せずに、数十年前の社会構造を
念頭に置いたままで、データを分析したり
議論したりするからうまくいかないのだ。
「家族は何人?」と質問すると、
ほとんどの人が同居している親族のみの数を
答える。しかし、それは「世帯」であって
家族ではないだ。
携帯電話はインターネットの普及の影響で、
いつでも連絡が取れる。
車や公共交通機関が発達し、離れて暮らしている
子どもなどの世帯も含めて“家族”とするべき。
以上、「FMK Morning Glory ヒューマン・ラボ
熊大ラジオ公開授業・知的冒険の旅」でした。