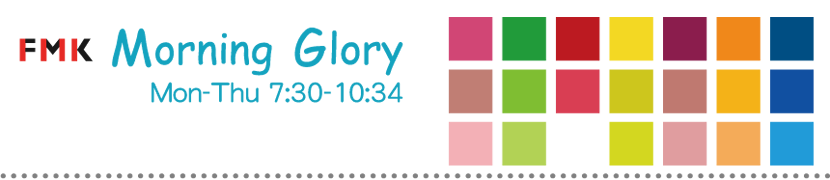9月3日(木)の名盤は…
今日は1970年代のポップ・チャートを大いににぎわせた
イギリスのヒット・メイカー「レオ・セイヤー」を紹介しました。
ほぼ同時期に人気のあったエルトン・ジョン、ギルバート・オサリヴァンと並んで、
イギリス男性シンガーソングライター三羽ガラスといったイメージですが、
この3人、実はそれぞれ特徴があります。
シンガーソングライターといっても詞・曲ともに完全に一人で作るのは
ギルバート・オサリヴァン。
エルトン・ジョンは作曲中心で、詞はほとんど相棒のバーニー・トーピンのもの。
そしてこのレオ・セイヤーは逆に作詞中心で、
作曲はその時々のパートナーに任せています。
それどころか他人の作った歌を歌うことにも抵抗のない人で、
カバー・ヒットも多いです。
純粋なシンガーソングライターというよりも、作詞能力の大変優れた
歌手兼パフォーマーと呼ぶほうがしっくりくるようです。
ですから誰と組んで曲を作るか、そして誰にプロデュースされるかで
色合いがずいぶんと変わってしまうところがあって、
これが彼の長所でもあり、短所でもあるかもしれません。
でも誰と組もうが、決して変わらないものもあります。
それは、喜劇と悲劇の境界線を効果的に行き来すると称される、
悲しいのに笑える、おかしいのに涙が流れるような、とてもイギリス的な歌詞。
このへんが日本では言葉の壁のせいか、どうも伝わりにくくて、ちょっと残念です。
今日紹介するのは、誰からも見向きもされないストリート・ミュージシャンが
道ゆく人々に“旦那、1曲いかがです?明るくいきましょうよ。
そのかわりお金を恵んで下さいよ”という
やり取りを通じて庶民の人生の悲哀をユーモラスに、
かつ優しい視線で描いた名曲です。
こういう表現を書かせたら右に出る者はいませんし、
まさにこういう歌を歌うために神様に与えられたような、
明るく物悲しさをたたえた声質がたまりません。
お届けしたのは、レオ・セイヤーで「ワン・マン・バンド」でした。