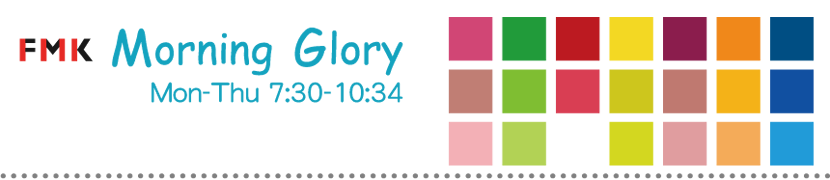3月31日「ザ・フー」
20年以上前、ある有名ミュージシャンが語った言葉があります。
“音楽なんてものは力が弱いから、本当にダウンしたとき、
例えば盲腸だとか足切ったときに音楽なんか聴けない“というものです。
悲しいことにこれは絶対的真理でしょう。
私たちはこの3週間、この言葉の重みを痛感しています。
FMもAMも、キー局もローカル局も、全国すべてのラジオマンが、
それぞれに多くの思いと願いを込めて選曲しているはずですが、
同時に音楽の力の限界と自分の無力さも思い知らされているかもしれません。
家族や財産を失った人々に届ける音楽なんてないのです。
それでも“The Show Must Go On.”、
ショウは続けなければならないのならば、
せめて音楽を聴ける程度に元気がある人を癒し、
勇気づけ、ほんの少し後押しできるものでありたい。
そう、音楽には悲しみの底にいる人を救えるほどの力はないですが、
少し回復して前を向き始めた人に寄り添い、支えるくらいの力はあるのです。
微力だが無力ではない。
過去を振り返っても、関東大震災、終戦後、阪神淡路大震災等の後に
復興を支えた大衆歌、ヒット曲がありましたし、
そんな大きなムーヴメントじゃなくとも、
その時代を生き抜いた個人個人の胸に鳴り響く
自分だけの活力の音楽があったと思うのです。
実は冒頭のミュージシャンの言葉には続きがあります。
“だけど、それに近いことになっても通用するレコードが何枚かある。
そういうものに出会えたことはすごく幸運だと思う”。
(ちなみにこれらの言葉、山下達郎さんの言葉です。)
皆さん、一緒にそれを探しましょうよ。
ちょっとヘヴィな状況でも、それを聴くと“人生捨てたもんじゃないな”と思える
自分だけの“今日の名盤”を。
そのお手伝いをするのもラジオの使命だと私は信じています。
今日お送りしたのは、一言で言えば音楽に信仰に近い思い込みを持った
世界一の真摯な音楽バカ・バンドが、
“何故私達は音楽を演るのか”を高らかに宣言し、
“音楽の可能性を信じる”と決意表明した名盤です。
文学的・哲学的で難解な内容ですが、私はそう解釈しています。
そうとしか聴こえませんし、この生命力溢れる楽曲と演奏を前にすると
“それならこっちも死ぬまで聴き続けてやろうじゃないの”と思えてくる、
そんな曲です。お届けしたのは、
1974年の曲、ザ・フーで「ピュア・アンド・イージー」でした。