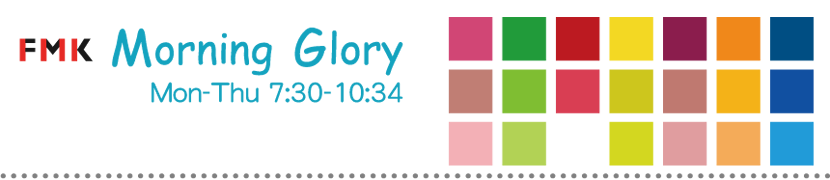8/26 ビートルズ登場前のイギリスの音楽シーン
今月は、夏休み特別企画「生まれる前の音楽を聴いてみよう」として
お送りしてきました。最終回の今日はビートルズ登場以前の
イギリスの音楽シーンについてお話しました。
1962年10月、ビートルズがシングル「ラヴ・ミー・ドゥ」でデビュー。
ここからイギリスのロックン・ロールの歴史が大きく変化したことは
言うまでもありませんが、“歴史を書き換えた”のであって、
ここから歴史が始まったわけではないことは忘れられがちです。
当然、10代の頃のビートルズのメンバーたちを夢中にさせた
ロックン・ローラーがいたのです。
もちろん、その大半はアメリカからやって来た人たちでした。
でもそれは仕方ないことなのです。
ロックン・ロールは1950年代中期にアメリカで誕生した音楽なのですから。
イギリスも最初は日本と同じくロックン・ロールの輸入国で
しかなかったのです。このころのイギリスのヒット・チャートは、
もともとイギリスにあった大衆音楽と
アメリカ産のロックン・ロール、エルヴィスやエディ・コクラン、
バディ・ホリーといった人たちが混在するようなものだったそうです。
イギリス人にとって初めての身近なヒーローは、
1956年「ロック・アイランド・ライン」のヒットを放ったロニー・ドネガン。
これはまだロックン・ロールではなく、スキッフルと呼ばれる音楽で、
生ギター、バンジョー、洗濯板、茶箱で作ったベースなどを使った
「Do It Yourself」の精神にあふれたものでした。
スキッフル・ブームは2年ほどで終わってしまうのですが、
エレキギターなんか夢のまた夢という10代のイギリスの子供たちにとっては
自分で音楽をやろう、と思わせる絶大な影響があったのです。
ビートルズもスキッフルが出発点だったことは有名です。
このブームで楽器を演奏する楽しさに目覚めた若者たちに
エレキを手にする意志を固めさせたのが、
1958年デビューのクリフ・リチャードです。
爆発的人気を得た、という意味では、イギリス人ロックン・ローラーの第1号が
この人であるのは間違いありません。
この人自身はティーンエイジ・アイドルの側面もあり、
甘いポップスを歌うこともあったのですが、
バック・バンドのザ・シャドウズの存在がイギリス産ロックン・ロールの
元祖としての地位を強固にします。
クリフ・リチャードとザ・シャドウズこそ、イギリス産ロックン・ロール・バンドの
第1号なのです。
特にギターのハンク・マーヴィン。
1960年から1970年代のイギリス人ギタリストは
100%彼の影響を受けているといっていいでしょう。
スキッフルで音楽を始め、シャドウズに憧れてエレキを練習した人たちが、
後のブリティッシュ・ロック黄金時代を築くことになるのです。
クリフはビートルズに先駆けた4年間でNo.1を8曲、
25枚がシルヴァー・ディスク以上を記録し、
ビートルズ以前は完全にクリフとシャドウズの時代だったのです。
そして現在も現役で国民的スターに君臨しています。
お届けしたのは、
1959年の曲クリフ・リチャード&ザ・シャドウズで「ダイナマイト」でした。