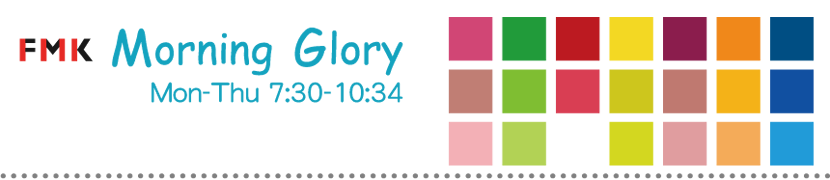11月12日(木)の名盤は…
“ロックはブルースから生まれた”とよく言われます。
半分正解です。
ロックは黒人音楽であるブルースを父に、
白人音楽であるカントリーを母に生まれました。
この辺りの詳しい話は、日を改めてじっくりしたいと思いますが、
ロックのルーツをたどっていくとブルースに着くのは間違いありません。
ロックを演奏するのは基本的に白人がメインなので、
もともとカントリーは自分達のルーツとして
持っているので問題はないのですが、後追いで学習したブルースに対しては
長い間コンプレックスを持っています。
極論するならば、本当はブルースをやりたいのだけれど
黒人みたいに上手くできないので
得意な白人音楽の要素を加えて再構築した”ぎこちなさ”こそが
ロックの面白さなのですが、
やはりミュージシャンとしてはそうもいかないのでしょう。
ブルースに始まりR&B、ソウル、ファンク、ディスコ、ヒップ・ホップ、ハウスなどと、
黒人音楽の新しい動きがある度にロックはそれをマネし、
取り入れてきたのは劣等感の表れでした。
でも本当はそれらの新しい音楽は白人音楽に影響を受けた
黒人音楽だったのに気付く人は少なかっただけなのです。
1980年代にロバート・クレイという黒人ブルースマンが登場しました。
低迷するブルース界の救世主として黒人側からも期待の大きかった人ですが、
この人の音楽がまぎれもないブルースなのに、
何かとってもロックっぽかったのです。
それもそのはず、彼は少年時代ビートルズに憧れてギターを手にし、
ロックを聴いて育ったのでした。
ブルース直系ではなく、ブルースに憧れた白人ロッカーから
影響を受けた黒人ブルースマン。
ロバート・クレイの登場と、それが白人、黒人両方のファンから支持され、
ブルースとして破格の大ヒットとなったことで
コンプレックスから解放されたロッカーはとても多かったのです。
今日お届けした曲は、ザ・ロバート・クレイ・バンドの
1986年全米22位の曲「スモーキング・ガン」でした。