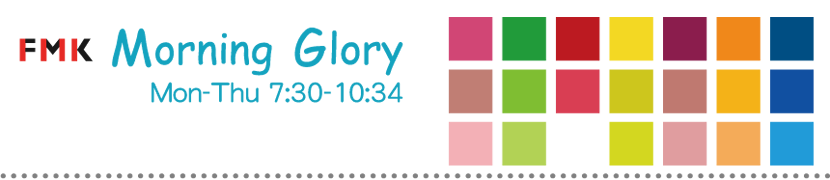6/17 「ソロ」
今日は、1990年代、ソウル・マニアから”救世主”と呼ばれ、
熱烈な支持を受けたボーカル・グループ、ソロを紹介しました。
先日、彼らが再結成して、8月には来日公演まで行なうというニュースが
発表されました。
決して大ヒットを記録したわけではなく、
実質3年間の活動で2枚のアルバムしか残していないにもかかわらず、
彼らの復活を喜ぶファンの声があちらこちらからたくさん聞こえてきます。
それはなぜなのでしょう。
もちろん、まず第一には彼らの実力が飛びぬけていたこと。
実は90年代は意外と男性ボーカル・グループは実力派揃いだったのですが、
その中でも彼らの上手さは頭ひとつ、いや頭ふたつくらい抜きん出ていると
言われていました。
そしてもう一つは当時の音楽背景を思い出してみる必要があります。
90年代のブラック・ミュージック界はヒップ・ホップという大きな柱があって、
それ以外のラップではない歌モノ、いわゆるR&Bとの二本柱でした。
で、このR&BはHip Hop以降の新しい感覚が前面に出ていて、
1960年代、70年代から脈々と続くソウルの伝統から外れているかのような、
ちょっと別の流れのような感触があったんです。
そうなると当然、そのスキ間を埋めようと、伝統的ソウルの流れを汲んだような
R&Bが生み出されてきます。
”ニュー・クラシック・ソウル”と呼ばれる動きがそれで、
ソロもその流れから出てきたのは事実ですが、他のほとんどが、
「ちょっと70年代風味を取り入れてみました」といった感じでしかなかったのに対し、
彼らは実にストレートに伝統を踏まえた、古き良き時代のソウルと直結した歌を
聴かせてくれたのでした。
だからこそ“最近のR&Bってやつはどうも・・・”というオールド・ソウル・マニアに
救世主として受け入れられたのです。
1972年の大ヒット、ドラマティックスの「イン・ザ・レイン」をサンプリングしたこの曲も、
嫌味ではなく必然性が感じられるのです。
今日お届けしたのは、ソロで「エクストラ」でした。